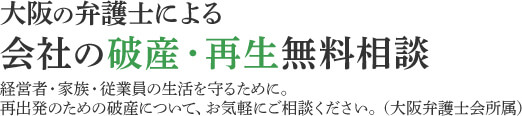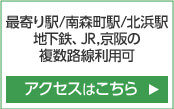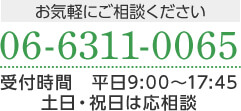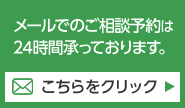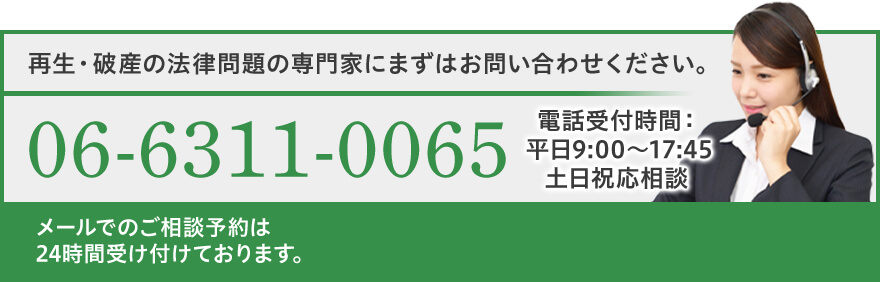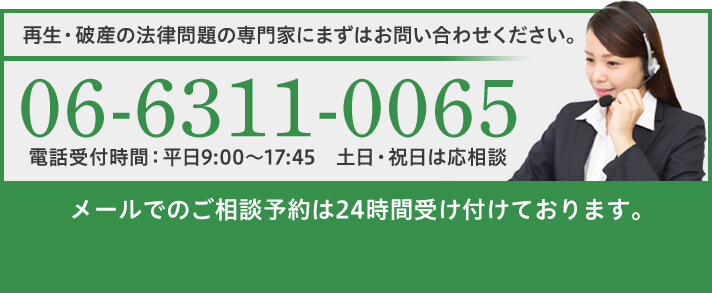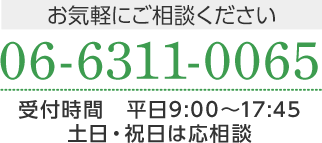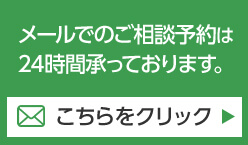Contents
飲食店の厳しい現実と廃業の背景
飲食業は,初期投資が抑えやすいこと,政府系の金融機関の初期融資額と初期投資額のバランスが取れていることから,一見、新規参入が容易な業種といえます。
しかし,ご存知のように,飲食業の競争の厳しさは折り紙つきで,開店後10年間存続している店舗は10%とも言われています。
また,当初は流行に乗って,売り上げも上がり,多店舗経営に乗り出したものの,その後の売上の減少により破産に至ったり,最近は,人手不足による廃業などという事案も目にします。
特に、人手不足により営業時間や営業日数を減少せざるをえなくなり、その結果売り上げが下がり、他方、食材や燃料の増加を価格にも転嫁できず倒産に至るという事例を非常によく見ます。
飲食店が破産に至る場合の特徴
飲食店が破産に至る場合次のような特徴があるといえます。
(1) 解雇予告手当が高額になりがちである
飲食業の場合,スタッフにアルバイトを多数雇用している場合があります。
破産予定を理由にアルバイトを解雇する場合も,法律上は解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当は「直近3ケ月の給与の平均」と説明されることが多いのですが,実は,最低保証の規定が定められており,出勤日数の少ないパートアルバイトに対しては,この規定が適用されます。
具体的には(直近3ケ月の総賃金)÷(直近3ケ月の労働日数)×60%×30日という計算式を使います。
その結果,解雇予告手当が直近3ケ月の給与の平均より高額になることがよくあります(破産をご決断される際には,解雇予告手当の確保を十分に行っていただきたいと考えております)。
(2) 立替払いの対象とならない可能性
上述のように飲食店はアルバイト従業員が勤務していることが多く、特に学生のアルバイトの場合、毎月の賃金が少額になることがしばしばあります。
賃金が未払いの場合で、かつ会社に支払いの資力がない場合、労働者健康安全機構による賃金の立替払いの制度があります。
しかし、未払い賃金が少額の場合(2万円未満の場合)、立替払いの対象とはならないので注意が必要です。
(3) 従業員への連絡
また、アルバイトの従業員はシフト制で勤務しているので、破産の準備に入った日(いわゆるXデー)に、出勤していないこともままあります。
そのため、破産の準備に入るとともに連絡網を作るなどして、当日出勤していないアルバイト従業員にも破産準備に入ったことなどの連絡をする必要があります。
従業員によっては、店舗のロッカーに私物を保管している場合がありますので、別途弁護士が立ち会って、私物の引き渡しなどを行う必要が生じます。
(4) 食材の廃棄について
さらに、食材については放置していると腐敗してしまい衛生上の問題が発生することがあります。
そのため、破産準備の中で速やかに廃棄を進める必要がありますので、廃棄費用の確保が必要となります。
廃棄業者を手配する場合でも、実際の作業まで1,2週間必要なことがあり、その間に食材が腐敗することも防がなければなりません。そこで、その間の電力を確保することも必要になります。
(5)リース物件
また,厨房機器がリース物件であることがよくあります。
リース物件は弁護士がリース会社と調整の上,返還しますが,例えばキッチン内で組み立てたような物件の場合,搬出が不可能なケースもあり,予め現物を見せていただいて,リース会社との調整をさせていただくことをお願いいたします(特殊なオーブンなどを導入しておられる場合はお知らせください)。
最後に
破産費用に関しては,窮境にある企業様は,売上の減少,賃金の支払いなどにより,既にキャッシュフローが減少していることがあり,破産費用の捻出に苦慮される場合があります。
飲食店の場合。すでに述べましたように、破産にあたって従業員への支払いなどが問題になることが多い一方、日々の現金収入があることから判断の遅れにつながっていることもありえますので,ご注意いただければと思います。